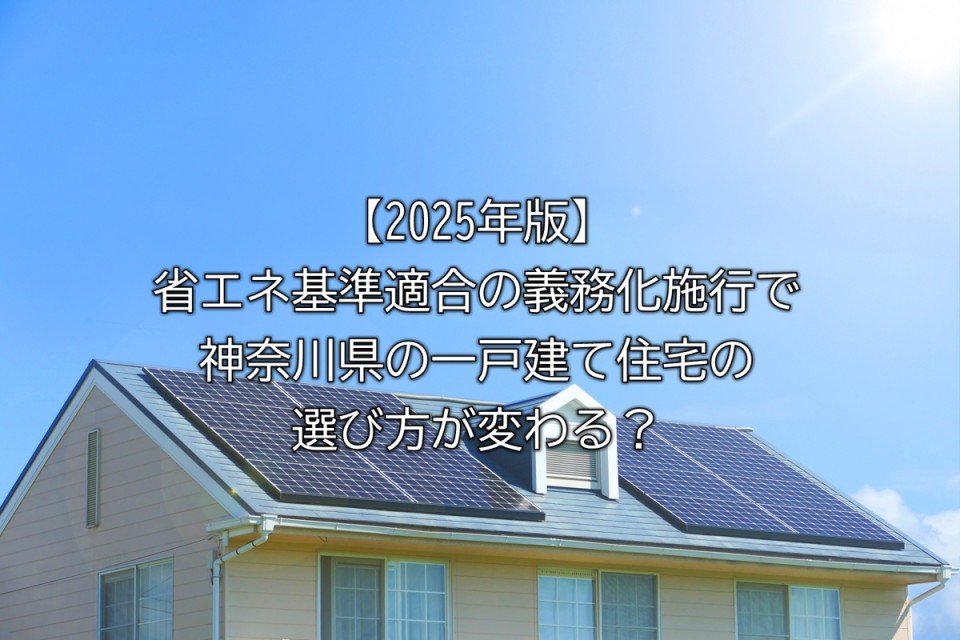
目次
2025年4月以降に着工する、ほぼ全ての新築住宅は、省エネ基準適合の義務化の対象となります。
これまで大規模な住宅や特定の建築物にのみ適用されていましたが、今後、新築される一戸建て住宅には一定の省エネ性能の確保が求められます。
省エネ基準適合の義務化は、住宅購入者にとって家選びの考え方を見直すよい機会です。
そこで今回は、省エネ基準適合の義務化が施行された後に一戸建て住宅を購入する方へ、その概要や省エネ住宅のメリット、家選びのポイントなどについてお伝えします。
省エネ基準適合の義務化とは
省エネ基準適合の義務化は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正(令和4年6月公布)によるものです。
主な改正点の中に、建築主の性能向上努力義務があります。
エネルギー消費性能の一層の向上を図ることを指しますが、一層の向上とは、義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能の確保を意味します。
施行の背景
省エネ基準適合義務化は、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」と、「2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減する」という目標達成の重要な施策の一つとの位置づけです。
地球温暖化対策を強化するため、大規模な建築物だけでなく、個人住宅においてもエネルギー消費量を削減する取り組みが急務となっています。
5年後の2030年には、省エネ性能の基準がZEH水準へと格上げされることも、ほぼ決定と考えてよく、さらなる高性能な省エネ住宅への布石ともいえます。
省エネ基準適合義務化の必要性
実質的に、新築される住宅はすべて一定レベル以上の省エネ性能を持つことになる、省エネ基準適合の義務化の施行は、エネルギー消費量削減と環境負荷軽減に大きく寄与することが期待されています。
その理由は主に2つです。
1つ目は、日本のエネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策の推進が挙げられます。
家庭や業務部門のエネルギー消費量は依然として高い水準にあり、建築物の断熱性能向上や高効率設備の導入によって、大幅なエネルギー消費削減が見込まれるからです。
2つ目は、木材需要の約4割を占める建築物分野における、木材利用の促進にあります。
もともと日本の住宅仕様においては、加工のしやすさやリラックスできる空間をつくるために、木材が多く使用される傾向です。
国産の木材を活用すれば林業の活性化にもなりますし、樹木が大気中から取り込んだ二酸化炭素は、住宅用木材になっても貯蔵したままという特性もあり、環境対策につながります。
省エネ基準適合住宅を探すなら、神奈川県の一戸建て住宅情報からどうぞ。

省エネ住宅のメリット
省エネ基準に適合した住宅をはじめ、ZEHやGX志向型住宅の普及が進むと、単なる法令遵守以上に多くのメリットをもたらします。
環境への配慮だけでなく、長期的な経済的利益や快適な暮らしの実現、さらには将来の資産価値にまで好影響を与える可能性があるからです。
神奈川県下の新築一戸建て住宅も、4月以降に着工する物件は、ほぼ省エネ住宅といえます。
改めてメリットを確認しておきましょう。
光熱費の削減
省エネ住宅のメリットで最も期待されるのは、光熱費の大幅な削減です。
高い断熱性能を持つ住宅では、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を維持するために必要なエネルギーが少なくて済みます。
神奈川県(省エネ基準地域区分6)においては、標準的な省エネ住宅とZEH水準では、年間で46,000円(出典:年間の光熱費も節約できる!|経済的にオトクに!|家選びの基準変わります - 国土交通省)もの差がでると国土交通省は試算しています。
太陽光発電システムを備えた省エネ住宅であれば、さらにエネルギー消費量の低減が見込めますし、蓄電池も設置すれば自家消費も含めて消費の効率性を高めることも可能です。
この効果は、住宅の寿命である数十年間にわたって継続するため、長期的に見ると相当な経済的優位性が得られます。
資産価値の維持
省エネ性能の高い住宅は、将来的な資産価値の維持・向上にも寄与します。
特に、省エネラベルや住宅性能評価などの第三者評価が付いている住宅は、その性能が「見える化」されているため、中古住宅市場での評価も高くなります。
ただし、資産価値を維持するためには、メンテナンスを含めた適切な維持管理が不可欠です。
省エネ住宅とはいえ建物自体の経年劣化は防げませんし、省エネ設備も寿命があり、定期点検や故障・修理・部品交換といった費用の負担も発生します。
省エネ性能を長期間にわたって維持できれば、資産価値の下落を抑制することができます。
補助金制度の活用
省エネ住宅の購入に関しては、国や地方自治体からさまざまな補助金制度が用意されています。
やや割高の傾向にある初期費用の負担を軽減し、資金計画で欠かせないほど重要です。
国が支援する「子育てグリーン住宅支援事業」では、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEHが対象となっていますが、今現在の省エネ基準の住宅は該当しません。
-
GX志向型住宅:160万円
-
長期優良住宅:80万円
-
ZEH:40万円
名称には「子育て」と付いていますが、対象世帯の区分は以下のとおりです。
子育て世帯とは、申請時点において子を有する世帯で、子は平成18(2006)年4月2日以降の出生もしくは平成17(2005)年4月2日以降の出生に限ります。
若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが昭和59(1984)年4月2日以降の出生もしくは昭和58(1983)年4月2日以降の出生が条件です。
申請については、ハウスメーカーや住宅販売会社といった事業者が担うため、サポート体制が整っているかを確認しましょう。
優遇制度の活用
税制面や住宅ローンの金利においては、省エネ住宅に対する優遇制度の活用で、長期的な経済的負担を軽減することができます。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、所得税の減税に大きな役割を果たしますが、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たさなければ利用できなくなっています。
ゆえに、2025年に入居予定で新築住宅を購入するならば、住宅ローン減税が適用できるか、ハウスメーカーや販売事業者に確認を忘れないようにしましょう。
固定金利の住宅ローン「フラット35S」では、省エネ性能の高い住宅に対して、一定期間金利が引き下げられることが特徴です。
自治体独自の制度も併用できるかどうかの情報収集も欠かせません。
ゆえに補助金に関する情報に詳しい、申請実績も豊富なハウスメーカーであれば、資金計画の面で有利な情報が得られる可能性が高くなります。
来店予約もできる、神奈川県の一戸建て住宅情報サイトを利用して、相談してください。

省エネ住宅選びのポイント
省エネ住宅を購入したい方々にとって重要なのは、単に基準をクリアしているだけでなく、将来を見据えた賢明な選択をすることです。
住宅は数十年にわたって使い続ける大切な資産と考えて、初期費用だけでなく、将来的な制度変更や省エネ性能の進化も考慮に入れた選択が求められます。
ここでは、省エネ住宅選びにおける重要なポイントを解説します。
省エネ性能で判断
最も重視すべきは客観的な省エネ性能の評価で、住宅の断熱性能やエネルギー消費効率を分かりやすく数値やランクで表示しているため、非常に有効な判断材料となります。
その表示とは、建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度(BELS:ベルス)に基づく省エネ性能ラベルで、以下のような情報が記載されています。
ラベルとはいえ建物に貼り付けられるのではなく、紙面広告やウェブサイトの個別物件紹介ページでの表示です。
評価方法には、ハウスメーカーなどが行う自己評価とBELS評価機関による第三者評価があります。
家選びにおいては、任意項目である目安光熱費が表示されている、第三者機関での評価であることが望ましいといえます。
来たるZEH水準を考慮
今の省エネ基準は、あくまでも最低限のラインであり、今後、基準は段階的に引き上げられていく見通しです。
2030年にはZEH水準が標準になることは、ほぼ、間違いないと考えます。
改めてZEHとは、高断熱化と高効率設備の導入によりエネルギー消費量を大幅に削減し、さらに太陽光発電などでエネルギーを創り出すことで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅です。
現在の省エネ基準よりもさらに高い性能を持っています。
今の時点で一戸建て住宅を購入する場合、将来の基準引き上げを見据えて、ZEH・長期優良住宅・GX志向型住宅などの上位基準を満たす住宅を選ぶことは、賢明な手段のひとつともいえます。
実績のあるハウスメーカー
省エネ住宅、特に高性能なZEH以上の住宅を選ぶ際には、実績のあるハウスメーカーや工務店を選ぶことが非常に重要です。
省エネ住宅の性能は、設計図面上の性能だけでなく、実際の施工精度によっても大きく左右されます。
特に高い気密性や断熱性を実現するためには、施工技術や品質管理が極めて重要です。
実績のあるハウスメーカーは、一般的に以下のような特徴を持っています。
弊社リブワークはZEHビルダー登録を行い、2025年度に向けたZEH普及率の目標を75%としています。
ハウスメーカー主催の省エネ住宅に関連する完成見学会や相談会への参加は、直接、貴重な情報や助言、特典など得られるよい機会のため欠かせません。

まとめ
2025年4月1日からスタートした省エネ基準適合義務化は、日本の住宅市場と環境対策における重要な転換点となります。
この制度の施行により、すべての新築住宅は一定レベル以上の省エネ性能を持つことが法的に求められるからです。
住宅選びもデザインや機能性を中心とした考え方から、省エネ性能と長期的な経済性も含めて多角的な視点での判断が必須といえます。
今回の省エネ基準適合義務化はあくまでもスタートラインです。
2030年にはZEH水準が標準となることもふまえて、神奈川県での土地探しは、リブワークのe土地netにお任せください。
また、神奈川県で省エネ住宅の建築を希望される方で、土地情報をお求めの方はリブワークにぜひご相談ください。